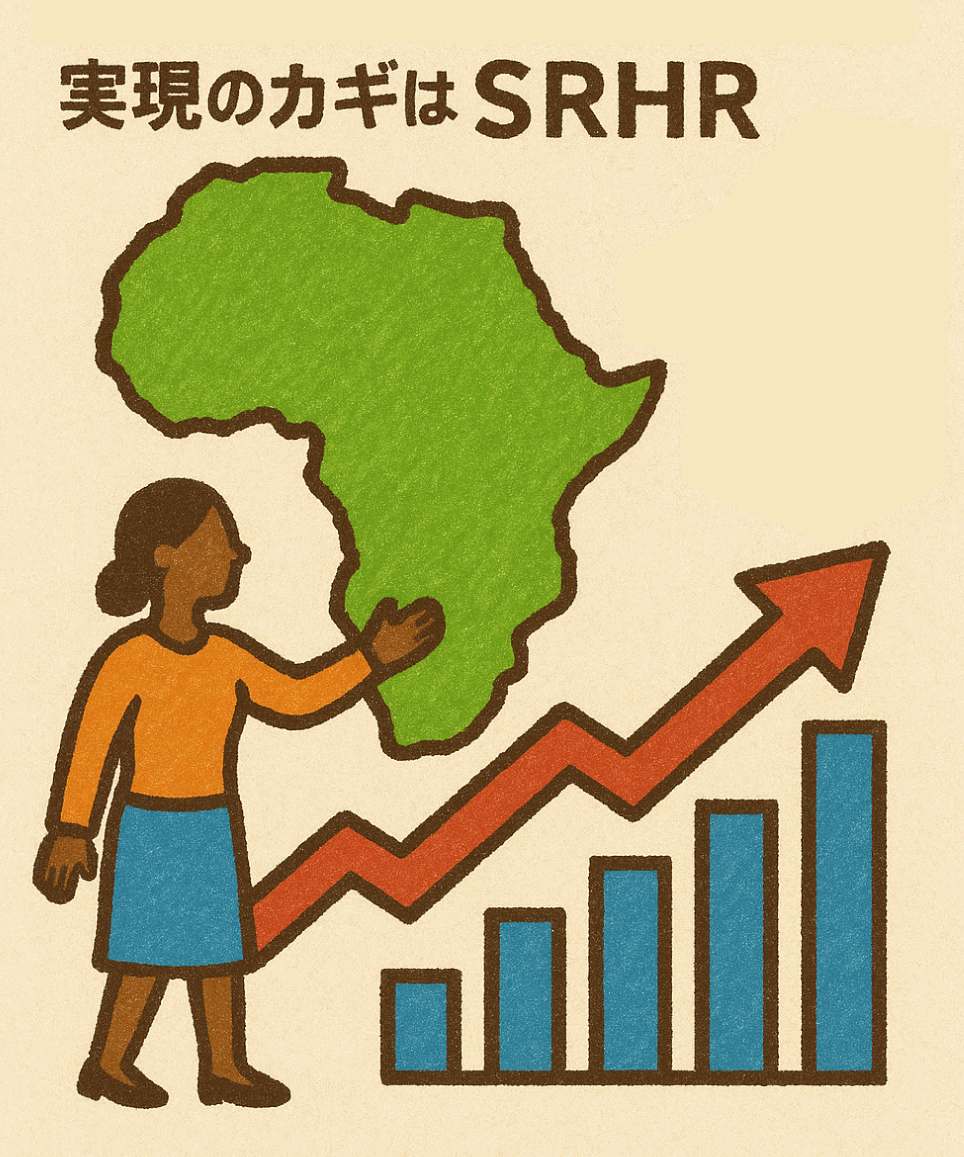
第9回アフリカ開発会議(TICAD9:2025年8月20日~22日横浜で開催)において、国際家族計画連盟(IPPF)主催のサイドイベント「アフリカの解決策で逆風を乗り越える:経済成長と人間の安全保障実現のカギはSRHR」が、8月21日(木)に行われ、ジョイセフはUNFPA(国連人口基金)とともに共催しました。
米国政権交代の影響を受け、今、アフリカにおけるセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)は大きな逆風に直面しています。本イベントでは、日本政府による支援の成果を振り返るとともに、危機を克服するために必要な投資や解決策について、多様なステークホルダーが議論を交わしました。

アフリカ開発の鍵はSRHR ~ 日本の国際連携とリーダーシップ発揮の重要性
冒頭に、あべ俊子 文部科学大臣、続いて喜多洋輔 外務省 国際協力局 国際保健戦略官、前外務大臣の上川陽子 衆議院議員、アルバロ・ベルメホIPPF事務局長、新たに国連人口基金(UNFPA)事務局長に就任したディエン・ケイタ事務局長代行(当時)が登壇。いずれもSRHRがアフリカにおける開発と人間の安全保障の基盤であることを強調し、国際社会の連帯と日本の積極的な関与が不可欠であると訴えました。
冒頭挨拶されたあべ文科大臣は、JPFP会長の上川議員とともに、これまで長年にわたり、IPPFおよびUNFPAを積極的に支援してきました。
外務省の喜多戦略官は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の実現には女性の健康保護が欠かせないと述べ、IPPFやUNFPAと連携しながらSRHR分野の支援を継続する方針を示しました。
上川議員は、サハラ以南アフリカに、妊産婦死亡の約7割が集中しており、その多くは予防可能であると指摘。女性・平和・安全保障(WPS)の観点からもSRHRは不可欠であり、「日本はこの分野でリーダーシップを発揮する」と表明しました。
ベルメホIPPF事務局長は、IPPFが152か国で2億3,000万人に提供してきたSRHRサービスのうち、6割がアフリカを対象としていると説明。日本の支援がアフリカのSRHRネットワークを支えていると評価し、同地域での緊急対応の必要性を強調しました。
ケイタUNFPA事務局長代行(当時)は、SRHRへの投資を「SDGs達成に直結する質の高い投資」と位置づけ、妊産婦保健サービスや女子教育、若年妊娠予防の重要性を指摘しました。
続くパネルディスカッションには、山口悦子ジョイセフ事務局長、ナルドス・ハゴスIPPFアフリカ地域事務局渉外部長、伊東直哉MSD株式会社アソシエイト・ディレクター、ブラッド・タイテル ゲイツ財団次長が参加しました。
アフリカ開発におけるSRHRの役割
前半はサントス・シミオネIPPFモザンビーク(AMODEFA)事務局長によるモザンビークのSRHRが直面する厳しい現状報告(録画)を皮切りに「なぜアフリカの成長にSRHRが不可欠なのか、そして今日の主要課題は何か」をテーマに議論が展開。
ハゴス氏は、米国の資金削減によりアフリカでの拠点閉鎖が相次ぎ、妊産婦支援やHIV予防サービスへのアクセスが失われていると説明。SRHRを人権として守ることが社会的・経済的発展の基盤になると述べ、政治的影響を排した支援の必要性を訴えました。
伊東氏は、MSD for Mothersの取り組みを紹介し、妊産婦の健康は女性本人だけでなく子ども・家族・地域社会、そして国家の長期的な発展につながると強調しました。
タイテル氏は、世界的にSRHR投資が1/2~1/3に減少している現状を示し、SRHRはアフリカ開発の「核」として優先的に取り組むべきであり、またその中で市民社会の果たす役割の重要性を強調しました。
さらにケニア、シエラレオネ、南アフリカのユースによるビデオメッセージも上映され、SRHRが若者の自立やコミュニティ形成に不可欠であり、正しい知識の普及がGBV(ジェンダーに基づく暴力)や望まない妊娠の防止につながること、自分たちとアフリカの未来をも左右することが共有されました。
危機をどう克服するか ~ 解決策と連携の在り方
アフリカの成長という文脈でSRHRは必要不可欠でありながら、危機に直面しているという現状を受け、パネルディスカッションの後半では、課題の解決策と各国・民間セクターの役割について議論が交わされました。
ハゴス氏はIPPFとして、アフリカのSRHRの危機的状況を喫緊の課題としてアフリカ以外の国や地域にも連帯を広げ、促すアドボカシーの重要性を強調し、厳しい状況に置かれながらも、SRHRサービスの提供を継続すること、そしてそのための適応力が重要であると語りました。
伊東氏はデータに基づいた質が高く効率的なSRHRサービスを提供し続けること、タイテル氏は世界各国、地域銀行・民間企業・NGO同士が連携することが、危機を乗り越え、SRHR課題を解決するために必要だと主張しました。
アフリカを中心とした各国・各組織の連携によるSRHR中心の開発を
パネリストによる議論の後、会場からは「アフリカでのSRHRサービスの提供における深刻な資金不足をどう解消すべきか」という質問が寄せられました。アルバロ・ベルメホIPPF事務局長は、アメリカのトランプ政権下でのグローバル・ギャグ・ルール*がもはやSRHRのみへの打撃に留まらないことを踏まえ、各分野横断で、世界各国と政府系組織・民間組織・民間企業が新たな形で連携し、課題解決のために協働することが重要であると回答しました。
*グローバル・ギャグ・ルール(GGR):正式名称「メキシコシティ政策」。1984年に共和党のレーガン大統領(当時)が初めて導入した米国の対外援助政策のひとつで、人工妊娠中絶に関するサービスを提供・推進する米国国外団体への、米国の資金提供の制限を規定したもの。共和党と民主党の政権交代に伴い、導入と廃止が繰り返され、2025年再選トランプ大統領により再導入され、GGRの適用範囲が大幅に拡大された。
IPPFのハゴス氏は最後に、アフリカを中心として各国・各組織が連帯し、人権を基盤に置き、SRHRを中心的な課題としてアフリカの開発に取り組んでいくべきだと主張しました。
閉会にあたり、ジョイセフの勝部まゆみ理事長は「SDGs採択時に生まれた全分野横断で、各国・組織が協働するという精神を今こそ取り戻し、政府・民間セクター・NGOが連帯を強めてSRHR課題に取り組むことが不可欠」と結びました。
- Author

JOICFP
ジョイセフは、すべての人びとが、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利:SRH/R)をはじめ、自らの健康を享受し、尊厳と平等のもとに自己実現できる世界をめざします



 アフガニスタンってどんなところ?
アフガニスタンってどんなところ? 「国際家族計画会議」ってなんですか?
「国際家族計画会議」ってなんですか?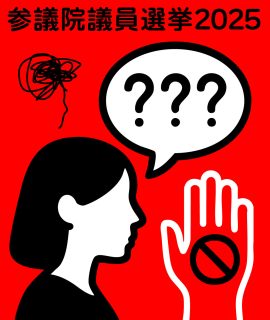 「高齢の女性は子どもが産めない」発言における3つの問題点 ー参議院議員選挙2025ー
「高齢の女性は子どもが産めない」発言における3つの問題点 ー参議院議員選挙2025ー