
支援の“いま”と“これから”を語る——ジョイセフラウンジ2025レポート
2025.9.24
- HOT TOPICS
- 実施レポート
- 企業/行政 連携プロジェクト
2025年7月23日、国際協力NGOジョイセフは、新たに移転したオフィスにて、支援企業を招いた報告会「ジョイセフラウンジ」を開催しました。
コロナ禍以降、直接対面で交流する機会は限られていたため、ジョイセフラウンジは“支援の輪”がリアルにつながる貴重な時間となっています。
新オフィスで初めての法人ゲストを迎え、会場には温かな空気と感謝の気持ちが満ちていました。
1.8カ国と日本をつなぐ|ジョイセフ2024年度の活動ハイライト
ジョイセフのパートナーシップグループ榎本より、2024年度の年次報告書をもとに、1年間の活動ハイライトが紹介されました。
ジョイセフは、アジア(アフガニスタン・ミャンマー・カンボジア)とアフリカ(ケニア・ウガンダ・ガーナ・ザンビア)、そして日本国内の計8カ国と1地域を対象に、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)を軸とした支援活動を展開しています。
この1年の主な成果は以下のとおりです。
- 保健医療従事者の育成人数:249人
- 保健ボランティアの養成人数:803人
- SRHRに関する情報が届いた人数:約31万人
- 医療機関でカウンセリングやケアを受けた人数:約13万人
これらの数字は、現場で活動する支援者や専門家、そして継続的にご支援くださる皆さまの想いと努力が形になったものです。

続いて、各国の代表的な取り組み事例が紹介されました。
- ケニアの取り組み──子宮頸がんの予防を地域から
-
ケニアでは、「子宮頸がんの予防啓発プロジェクト」に取り組んでいます。
医療従事者への研修、検査体制の整備、地域での啓発活動などを通じて、検診を受ける女性の数が大きく増加しました。予防と早期発見が命を守ることにつながることを、地域全体で共有しながら取り組んでいます。
- ザンビアの取り組み──暴力被害からの回復と自立支援
-
ザンビアでは、ジェンダーに基づく暴力(GBV)に対応するための支援を行っています。
「GBVストップセンター」や「セーフスペース」の設置、医療従事者や地域ボランティアへの研修、啓発活動を通じて、被害者が安心して支援を受けられる体制を整備しています。また、女性の自立支援として、裁縫などの生計向上技術を学べる研修も実施。日本から専門家を派遣し、現地での実践的な指導が行われています。
- ガーナの取り組み──母子保健と若者への情報提供
-
ガーナでは、「母子保健と子どもの栄養改善プロジェクト」を実施しています。
新たに診療所を建設し、医療従事者への研修を行うことで、より身近で信頼される医療の提供を目指しています。さらに、若者へのSRHRサービスの普及にも力を入れており、地域の教師やリーダーの育成を通じて情報提供体制を整えています。
あわせて、啓発ツールの配布や医療従事者の研修、保健管理委員会によるアクションプランの策定など、地域全体で取り組む包括的な支援体制の構築を進めました。
- ウガンダの取り組み──医療をすべての人へ届けるために
-
ウガンダでは、子宮頸がん検診をはじめとした医療サービスの強化を進めました。
医療従事者による「アウトリーチ活動」を通じて、村々を訪問しながら、検診や家族計画、HIV検査などのサービスを提供。
また、四半期ごとに活動を振り返るモニタリングと評価会を実施し、現場のニーズに即した支援の質を保つよう努めています。このように、ジョイセフの活動は、地域の現実と丁寧に向き合いながら、持続可能な変化を生み出すことを目指しています。
2.SRHRをめぐる国内政党の政策動向|最新アドボカシー報告
パートナシップグループディレクターの小野より、国内外における政策提言とアドボカシー活動の最新動向が紹介されました。

今回の報告では、ちょうど選挙直前というタイミングとも重なり、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)に対する各政党の政策方針を紐解きました。
主要政党が公表している政策集や公約の中には、予想以上に多くのSRHR関連項目が盛り込まれていることが確認できました。
以下は、主な政党のSRHRに関する政策のポイントです。
- 自由民主党(自民党)
-
- 女性に対するあらゆる暴力の根絶
- 妊娠前から出産・育児にかけての切れ目ない支援
- 困難な状況にある女性への包括的支援
- 性加害教員への再任防止など教育現場での対策
- 性的マイノリティへの配慮や健康支援を明記
- 選択的夫婦別姓には否定的な立場
- 立憲民主党
-
- ジェンダー平等を明確に掲げ、LGBT差別解消法の制定を目指す
- 選択的夫婦別姓や同性婚の法整備に積極的
- 国連女性差別撤廃条約の選択議定書の批准を公約に明記
- 公明党
-
- 学校における性の多様性を尊重する環境づくり
- 教員研修の充実と性教育の推進
- 妊娠前の健康支援(プレコンセプションケア)の推進
- 生理の貧困対策やSRHRに関する知識普及にも言及
- 国民民主党
-
- 若者から高年期の女性に至るまで一貫した健康支援を重視
- 性犯罪の厳罰化と加害者管理制度の整備を公約に
- LGBTや性的マイノリティの人権保障を明記
- 日本共産党
-
- 緊急避妊薬の無償化・低価格化と選択肢の拡充
- 中絶薬の導入と配偶者同意制の見直し
- 生理用品の無償配布と非課税化を明記
- 同性婚の実現や民法改正による法整備にも前向き
- れいわ新選組
-
- 多様な性や障害をもつ人々が直面する不平等の改善
- 「自分の身体を自分で決定する権利」を強調
- 性教育の保障やジェンダーに関する意識改革を掲げる
- 参政党
-
- 政策は一律ではなく、党員の意見をもとに個別に決定
- 明確なSRHRに関する方針は現時点では確認されず
- 社会民主党(社民党)
-
- SRHRの拡充や包括的性教育の重要性を一貫して訴える立場
- 日本保守党
-
- SRHRに関する政策や記述は確認されず
小野は、「こうした政策の違いを知ることは、私たちがどのような社会を目指したいのかを考えるうえで、とても重要な手がかりになります」と語りかけました。

ジョイセフでは今後も、SRHRをすべての人の権利として確立するために、行政・市民社会との連携を強化し、実効性ある政策提言を継続していく方針です。
3.アフガニスタン支援の“現場の声”──深まる困難と、現地に根差した支援のかたち
ジョイセフが長年にわたり継続しているアフガニスタン支援について、最新の状況と現在直面している課題について、パートナシップグループ柚山より報告が行われました。
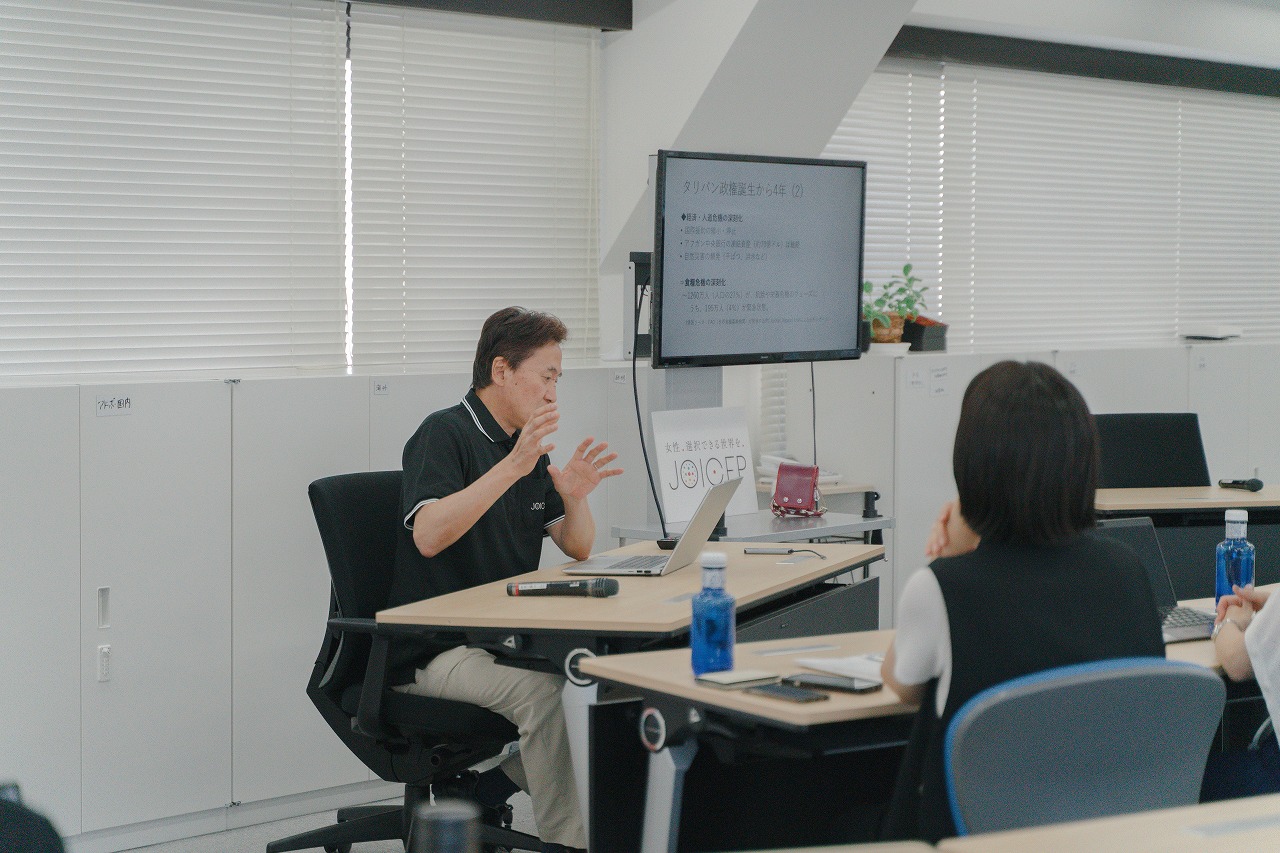
2021年8月にタリバンがアフガニスタンの政権を掌握してから、今年で4年が経過。その政変以降、現地の女性たちを取り巻く状況は急激に悪化しています。
- 2022年3月以降、中学校・高校での女子教育の禁止
- 女子の大学進学・通学も全面的に不可
- 教育の機会の制限
- 女性の公的機関やNGOでの就労は全面的に禁止
- 公園などの公共施設への立ち入りも禁じられ、「女性の社会的不可視化」が進行
こうした困難な状況の中で、ジョイセフは東部ナンガハール州において、現地のパートナー団体と連携し、「母子健康クリニック」の運営を継続。このクリニックでは、約4万人の住民を対象とし、1日あたり平均300人が受診する重要な医療拠点となっています。
スタッフの大半は女性で構成されており、女性医師、助産師、栄養カウンセラーなどが中心となって、女性や子どもが安心して医療を受けられるよう支援体制が整えられています。
クリニックで提供されている主なサービスは以下のとおりです。
- 妊婦健診・分娩ケア
- 乳幼児健診・予防接種
- 栄養改善指導・調理教室(地元の安価で栄養価の高い食材を使ったレシピの紹介)
- カウンセリング(家庭内暴力を受けた女性への心理的支援を含むSRHRカウンセリング)
- 健康教育・啓発活動
- 食糧配布(パンデミックや自然災害下での緊急対応)
近年では、分娩室の改修工事も完了し、より衛生的で安全な医療提供が可能となりました。
このような改善が実現したのも、長年にわたり寄せられた支援の積み重ねがあってこそです。
支援の輪を広げる企業の想い──電力総連様とクラレ財団様による取り組み
アフガニスタンにおける母子保健支援の現場には、企業や労働組合といった民間からの力強い後押しがあります。今回のジョイセフラウンジでは、活動を継続して支援くださっている2団体から、それぞれの立場での想いや取り組みもお話いただきました。
全国電力関連産業労働組合総連合(電力総連)組織局の金澤さんは、1995年から継続している募金活動「ふれあいカンパ」について紹介しながら、「ジョイセフとの連携は2007年から、そして2019年からはアフガニスタンの母子保健事業への支援を本格的に行っています」と説明されました。
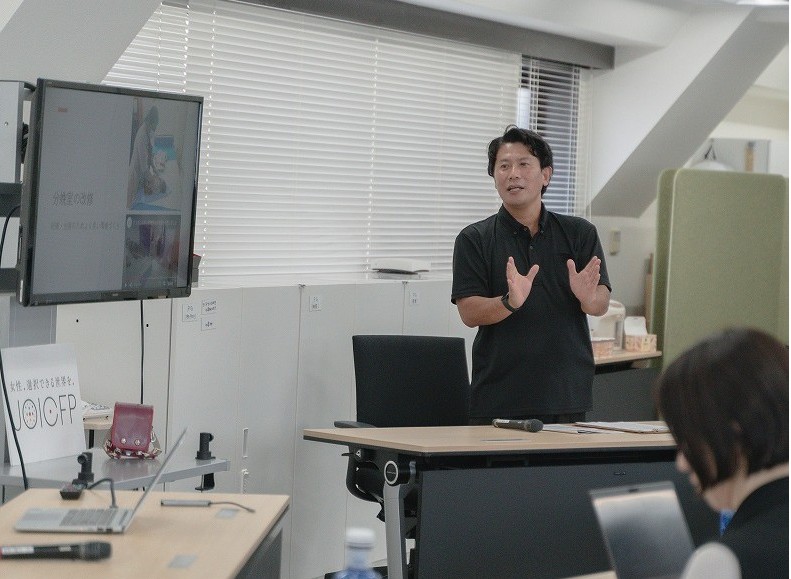
さらに、「他の支援は“自立”をゴールとすることが多いですが、ジョイセフのクリニックは“命を守る”という今この瞬間に必要な支援です。だからこそ、継続こそが最も重要だと感じています」と語り、現地医師とのオンライン対話を通じて「自分たちにできることは限られていても、支援を止めないことが何より大切だと実感しました」と強調されました。
また、一般財団法人クラレ財団の酒井さんからは、同財団が2017年より母子保健クリニックを継続して支えていることを報告されました。
「タリバン政権下で米国からの資金支援が停止され、現地の医療現場は非常に厳しい状況に置かれています」と現地の厳しさに触れながら、「ガザやウクライナは報道されますが、アフガニスタンの現状はメディアで取り上げられる機会が少ないのが現実です。その分、民間企業として支え続ける意味と責任を強く感じています」と語られました。
両者の発言からは、単なる一時的な寄付や協力にとどまらず、「必要とされている場所へ、継続的に関わり続けること」の重要性が強く伝わってきました。
4.ホワイトリボンラン2026、始動──“走るアクション”が生むエンパワーメントの輪
ジョイセフラウンジの後半では、ファンドレイジング推進担当の森田より、2025年の実績とともに、「ホワイトリボンラン2026」に向けた構想が初めて発表されました。
2025年は、国際女性デー制定からちょうど50周年という節目にあたります。
ジョイセフが2001年より活動を推し進めてきた「ホワイトリボンアライアンス・ジャパン」としても、大きな節目の年となりました。
同年3月のホワイトリボンランは、全国59拠点で開催され、バーチャルランと海外参加者も含めて4,583名が参加。
エントリー費からの寄付総額は558万円を超え、過去最大規模の成果を記録しました。
こうした成功を礎に、2026年にはホワイトリボンラン11年目の開催を迎えます。
2026年大会では、“数の拡大”ではなく“つながりの深化”に重点を置き、参加者との関係性をより丁寧に育てていく方針のもと、以下の目標を掲げています。
- 参加者数:6,000人
- 寄付目標額:650万円
- バーチャルラン参加者数:4,000人(前年比2倍)
新たなスローガンは「Run to Empower(走って力を届ける)」
走るという行動を通じて、すべての人が“自分らしく生きる力”を得られるようにという想いが込められています。

ビジュアル面では、ジョイセフが掲げる「選択の5色」を引き続き活用し、多様性や選択の自由を象徴するビジュアルとして展開される予定です。
森田は、「どこかで誰かがホワイトリボンランのTシャツを着て走っている、そんな日常の風景を全国で見られるようになれば嬉しいです」と語り、社会全体への広がりにも期待を寄せました。
また、2026年からは新たな試みとして「仲間エントリー制度」を導入。通常参加費は5,500円ですが、2人以上で申し込むと1人あたり4,800円になる仕組みで、代表者1名が最大5人まで申し込めるチーム参加型の制度となっています。
スケジュールは以下のとおりです。
- 2025年8月14日:拠点・協賛企業の募集開始
- 2025年11月4日〜2026年1月20日:一般参加者の募集期間
- 2026年3月1日、8日、9日:全国拠点ランを開催予定
- バーチャルランやSNSキャンペーンも例年通り実施
なお、2026年の寄付使途のテーマは「性暴力のない社会の実現」です。
ザンビアと日本の2カ国で、予防啓発を目的とした活動を展開する予定です。
加えて、東京マラソンにおいて毎年好評を博しているオリジナルステッカーの配布も、引き続き継続します。
森田は発表の最後に、「今年もまた、新たな気持ちでスタートラインに立ちたいと思っています」と笑顔で語り、会場に集まった参加者とともに2026年への第一歩を踏み出しました。
ブランドの想いを行動に──カシオ計算機株式会社様が語るホワイトリボンランとの共鳴
ホワイトリボンランの協賛企業のひとつであるカシオ計算機株式会社から、G-SHOCKブランドのマーケティングを担当されている松本祐貴さんに登壇いただきました。
カシオは「時計」「楽器」「教育」の3分野で事業を展開しており、その中でもG-SHOCKは“自分らしくあるために挑戦するすべての人を応援する”というグランドビジョンを掲げています。
松本さんは、この理念が「女性の健康と権利を守る」というジョイセフの活動と強く重なると感じ、2024年より支援を開始したと語りました。
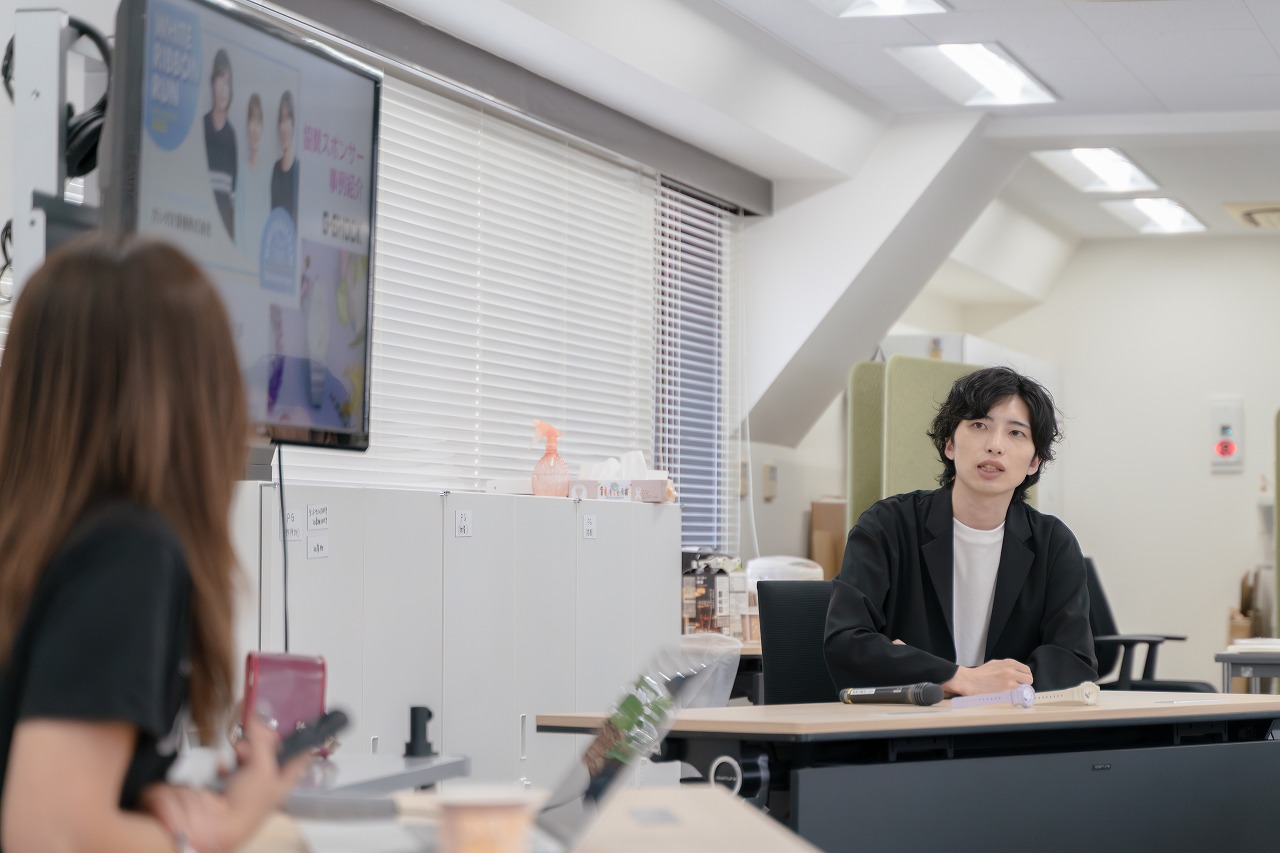
同社が初めてホワイトリボンランに参加した2024大会では、社員5名の参加からスタートしましたが、2年目となる2025年には参加者が約20名に増加。約半数は男性で、家族で参加された社員もいたそうです。参加者の多様性と社内での反響の大きさは、同社の取り組みに対する共感の広がりを物語っていました。
「このイベントを通じて、私たちのブランドビジョンを社内外に改めて共有できたと感じています」と松本さん。
千駄ヶ谷の拠点ではご自身もランナーとして参加し、「一番にゴールさせていただきました」と笑顔で振り返る場面もありました。
また、今年発表されたG-SHOCKのコラボモデルには、国際女性デーを象徴する“黄色と紫”のカラーを採用。
店頭では「こんな活動をしているなんて驚きです」「このモデルがきっかけで国際女性デーを知った」という声も寄せられたそうで、想像以上の反響があったと報告されました。
最後に松本さんは、「このようなコラボレーションが社会の新たなアクションにつながることを、私たち自身が実感しています」と語り、今後の取り組みへの意欲をにじませました。
5.支援の輪がつながる場となった温かな時間
閉会前には、全員での記念撮影と交流タイムが設けられ、支援者同士の会話や、新たな連携のきっかけが芽吹く時間となりました。
ジョイセフは、活動を通して「今を生きる命」に真摯に寄り添い、そして「未来を変える力」を引き続き支援者のみなさまと共に生み出していきたいと強く感じています。
これからも、世界と日本をつなぐ橋渡し役として、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)の推進に向けた歩みを止めることなく、丁寧に取り組みを進めてまいります。


